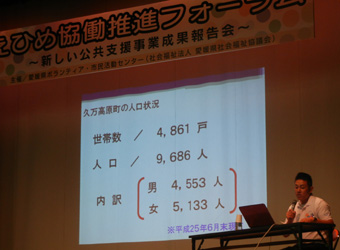‚WŒژ‚R‚P“ْپi“yپjپAˆ¤•QŒ§’jڈ—‹¤“¯ژQ‰وƒZƒ“ƒ^پ[‚ة‚¨‚¢‚ؤپu‚¦‚ذ‚ك‹¦“گ„گiƒtƒHپ[ƒ‰ƒ€پvپ`گV‚µ‚¢Œِ‹¤ژ–‹ئگ¬‰ت•ٌچگ‰ïپ`‚ھ
ٹJچأ‚³‚êپA“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚‰‚ژ‹v–œچ‚Œ´ژہچsˆدˆُ‰ï’|گX—m•مˆدˆُ’·‚ھ•ٌچگژز‚ئ‚µ‚ؤ”•\‚¢‚½‚µ‚ـ‚µ‚½پB
“–“ْ‚جپu‚¦‚ذ‚ك‹¦“گ„گiƒtƒHپ[ƒ‰ƒ€پv–{ژ‘—؟‚إ‚·پB
پi‚o‚c‚eƒfپ[ƒ^‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پjپ«

ڈ‘—ق‚ج‰و‘œ‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚o‚c‚eƒtƒ@ƒCƒ‹‚ھٹJ‚«‚ـ‚·پB
‚o‚c‚eƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً‚²——‚ة‚ب‚é‚ة‚حپAAdobe Readerپi–³ڈپj‚ھ•K—v‚إ‚·پB
AdobeژذƒTƒCƒg‚©‚çƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚·‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پB
ƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚ح‚±‚؟‚ç

گ¬‰ت”•\‚ً‚·‚é’|گXˆدˆُ’·
”•\‚جٹT—v‚حˆب‰؛‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
پyگ¬‰ت”•\پz
•ٌچگژزپF“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹in‹v–œچ‚Œ´ژہچsˆدˆُ‰ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆدˆُ’·پ@’|گXپ@—m•م
‡@‹v–œچ‚Œ´’¬‚جٹT—v
پ@ گlŒûپEپEپE9,686گlپi•½گ¬25”N6Œژ––Œ»چفپj
پ@ چ‚——¦43.72پ“‚إپAŒ§‰؛ˆê‚جچ‚——¦
‡A–¯ٹش‚ئ‚ج‹¦“‚ج‰آ”\گ«‚ئ•K—vگ«پiگV‚µ‚¢Œِ‹¤پj
پ@ ‹v–œچ‚Œ´’¬‚ج‰غ‘èپiچ‚—پA‰ك‘a‰»پAژq‚ا‚à•s‘«“™پjپپ’†ژRٹش’nˆو‚ج‰غ‘è
پ@ ‘½ٹٍ‚ة‚ي‚½‚é‰غ‘è‚ً‰ًŒˆ‚·‚邽‚كپAˆظ‹ئژيکAŒg‚ًگi‚ك‚é•K—v‚ھ‚ ‚éپB
‡Bˆظ‹ئژيکAŒg‚ة‚و‚éژہچsˆدˆُ‰ï‚ً‘gگD
پu“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹in‹v–œچ‚Œ´پv‚ًژہژ{‚·‚邱‚ئ‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA
پ@ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ً’ت‚µ‚ؤٹة‚â‚©‚بƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN‚أ‚‚è‚âپAچ،Œم‚جگV‚½‚ب
پ@‹¦“ٹˆ“®‚ج‰آ”\گ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ–حچُ
‡Cپw‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚èپx‚ئپw’nˆوژ‘Œ¹ٹˆ—pپx
پ@پ@‹cک_‚جŒ‹‰تپA‹v–œچ‚Œ´‚ج‰غ‘è‚âژو‚è‘g‚ف‚½‚¢‚±‚ئ‚حپw‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚èپx‚ئ
پ@پw’nˆوژ‘Œ¹ٹˆ—pپx‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚جƒLپ[ƒڈپ[ƒh‚ة‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚½پB
پ@پ@پںپw‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚èپx
پ@پ@پEچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ج•آ‚¶‚±‚à‚è—\–h‚â’nˆوƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBپ[‚ض‚جژQ‰ء—U”
پ@پ@پEژq‚ا‚à‚ج—ح‚ًژط‚è‚ؤچ‚—îژز‚â’nˆو‚ف‚ٌ‚ب‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚éژو‚è‘g‚ف
پ@پ@پںپw’nˆوژ‘Œ¹ٹˆ—pپx
پ@پ@پE”pچZگص’n‚ًٹˆ—p‚·‚邱‚ئ‚إپAگl‚ھڈW‚ـ‚èپA’nˆوٹˆ“®‚ھ‹N‚«پA’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚éپB
پ@پ@پE’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚إپAچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚جڈo”ش‚ھ•K‚¸–K‚ê‚éپB
پ@پ@پE’nˆو‚ف‚ٌ‚ب‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚èپAٹX‚àŒ³‹C‚ة‚ب‚éپB
‡Dچ،Œم‚ج‰غ‘è
(‚P)
چ،Œمژہچs‚µ‚ؤچs‚±‚¤‚ئ‚·‚邱‚ئ‚حپw•ںژƒپx‚ةŒ‹‚ر‚آ‚«‚ة‚‚پA’P‚ب‚éٹX‚أ‚‚è‚âپA
پ@ ٹX‚¨‚±‚µٹˆ“®‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBژہچsˆدˆُ‰ï‚ةڈ¤”„‚âٹX‚¨‚±‚µٹˆ“®‚ةڈ]ژ–‚µ‚ؤ
پ@ ‚¢‚é•û‚ھŒg‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚ا‚¤‚â‚ء‚ؤچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ج•ûپX‚ة
پ@ “ü‚ء‚ؤ‚à‚炦‚é‚ج‚©پB
(‚Q)
‹·‹`‚جپw•ںژƒپx‚©‚çچL‹`‚جپw•ںژƒپx‚ض
پ@پ@پw•ںژƒپx‚ئ‚¢‚¤‚ئپAڈلٹQژز‚âچ‚—îژز‚ج‚½‚ك‚ج‚à‚ج‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بƒCƒپپ[ƒW‚¾‚ھپA
پ@پ@•ںژƒگê–هگE‚â•ںژƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚¾‚¯‚إ‚حپA’nˆو‚إگ¶ٹˆ‚·‚éچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ًژx‚¦‚邱‚ئ‚ح•s‰آ”\پB
پ@پ@پ@‚»‚ج‚½‚ك–{ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ًژہژ{‚µپA’nˆو‚أ‚‚è‚â’nˆو—ح‚ج•K—vگ«‚ً‘i‚¦‚½‚ھپA‚ع‚₯‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@پ@’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚邱‚ئ‚إپAچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ج‹ڈڈêڈٹ‚âڈo”ش‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¢‚«پAچL‹`‚جپw•ںژƒپx‚ة‚ب‚é‚ئ
پ@پ@چl‚¦‚ؤ‚¨‚èپAچ،Œم‚ج‰غ‘è‚ئ‚ب‚ء‚½پB
‡Eچ،Œم‚جٹˆ“®
“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ژہچsˆدˆُ‰ï‚ح”“W“I‰ًژU
‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج“à—e‚ًˆّ‚«Œp‚¬‚ب‚ھ‚çگV‚½‚بˆدˆُ‰ï‚ً‘gگD‰»‚µ‚ؤŒں“¢ژہژ{—\’èپB
‡FگU‚è•ش‚èپi‚ـ‚ئ‚كپj
ژہچsˆدˆُ‰ï‚ً‘gگD‚µپAƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ًگط‚èŒû‚ئ‚µ‚ؤ‹¦“‚ج•K—vگ«‚ئ‰آ”\گ«‚ًŒ©ڈo‚µ‚½پB
‰غ‘è‚à‚ ‚é‚ھپA‹C‚أ‚«‚à‚½‚‚³‚ٌگ¶‚ـ‚ꂽپB
ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ƒeپ[ƒ}پu‹C‚أ‚«‚ئٹˆ“®‚جچL‚ھ‚è‚ً–عژw‚µ‚ؤپv
پE‹C‚أ‚«
‹¦“‚ج•K—vگ«‚ئ‰آ”\گ«
’nˆو‚أ‚‚èپi’nˆو•ںژƒپj‚ة‚و‚ء‚ؤƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBپ[‚ھŒ`گ¬‚³‚êپAچ‚—îژزڈلٹQژز‚ًٹـ‚ك‚ؤ
’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚èپAٹX‘S‘ج‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚éپB
پEٹˆ“®‚جچL‚ھ‚è
’nˆوژ‘Œ¹‚ًٹˆ—p‚µ‚½’nˆوچى‚è‚â‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚è‚ض‚جژو‚è‘g‚ف
پ¦“–“ْ‚ج—lژq‚حپAˆ¤•QگV•·‚ةŒfچع‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBپi‚XŒژ‚P“ْ•tپj
PDFƒfپ[ƒ^‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پBپ@پ@پu‚X.‚P•t.pdfپv‚ًƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh